くまごろうです。この投稿では資格取得のための概要を勉強スケジュールとともに解説していきます。
勉強方法の詳細は、各記事を参照してください。

この記事では資格取得のための概要を解説していくよ!
気になるところは、個々の解説を読んでね。
注意事項
くまごろうは「未経験の試験区分で連続合格をする」という目標で勉強をしていました。それなりに特殊な勉強を行ってきていると思うので、以下に注意してください。
注意事項① 試験への慣れ
最初に合格したデータベーススペシャリスト試験ですら、H23(午後Ⅱ不合格)とH24(午後Ⅰ不合格)のシステムアーキテクト試験を経ての合格なので、未受験からの合格ではありません。
最初に合格した論文系試験のプロジェクトマネージャ試験でも同様のことが言えます。
また午前試験は、応用情報技術者試験でしっかりと対策していることが影響し、午前Ⅱで出てくる共通系の問題の合格率はかなり高いです。
以降の解説では初学者を対象に解説を行いますが、説明が分かりにくいところがあると思います。その場合はご指摘をいただけれるとありがたいです。
注意事項② 勉強時間について
くまごろうの資格取得は「連続合格」にこだわっていました。結果、過去10回の受験で8回合格しています。
これを実現するためには、合格のボーダーラインからさらに一歩踏み込んで学習している必要があります。
くまごろうは1つの試験区分につき、感覚で200時間ほど対策を行っています。しかも新しい試験区分に挑戦すればするほど、対策の時間が伸びています。最初の論文試験だったプロジェクトマネージャ試験より、最後に受験したITサービスマネージャ試験のほうが学習時間は長いです。これはおそらくやり過ぎで、短くなるのが普通です。
人によって勉強の仕方は異なります。このブログは一般的な事例としてではなく、1つの事例として見ていただければと思います。
そもそも他者がどのような勉強の仕方をしているのかあまり知らないんですけどね。
また数年計画で資格を取得する場合の戦略と、今期必ず資格を取得したいと考えた場合の戦略は異なりますので、その辺も考慮していただけるとありがたいです。
注意事項③ 免責事項
くまごろうは試験対策の専門家ではありません。よって「資格の勉強方法」関連の記事の解説は、誤っている場合や効率的ではない場合があると思います。
このブログの解説は、1つの意見としてとらえていただければと思います。
正直に言うと、参考書も怪しい記述があったりするので、参考書を見比べてご自身で納得されながら勉強されることが重要だと思います。特に受験者の少ない試験区分は、参考書自体の競争もあまりないです。このブログも同様なので、その点はご留意ください。
合格までのスケジュール
合格までのスケジュールは、以下のようになります。
実際には論文試験や対象試験の業務経験の有無によって期間は変わりますので、その点はご留意ください。

記述系試験の場合は、論文対策の部分も記述対策を行っている形になります。
読書(春:12月~1月 秋:6月~7月)
初めに行う試験対策は、参考図書の読み込みです。
ここで読んでいるのは参考書ではなく、対象の試験区分の入門書や自己啓発本など、関係のある書籍を嫌にならない範囲で読んでいます。
例えば情報処理安全確保支援士であれば「暗号技術入門」とか、ITサービスマネージャーであればもっと軽く「『アポロ13』に学ぶITサービスマネジメント ~映画を観るだけでITILの実践方法がわかる!」などです。
このような参考図書を少なければ1~2冊、多ければ5~6冊くらい読んでいます。
詳しくは各試験の対策ページで紹介する予定ですので、そちらを参照してください。
また参考書を購入するのも同じ時期です。
こちらも紹介ページを作成する予定ですので、そちらを参照してください。
論文対策(春:2月~3月 秋:8月~9月)
論文対策で行う勉強は主に3つあります。
- 論文の骨子を作成する
- 論文を作成する
- 作成した論文を暗記する
くまごろうの場合は、論文骨子を10~15本くらい、論文を5~10本くらい作成しています。この本数自体は、出題テーマが絞り込めるかが影響しています。
このほかにも人によっては論文の書き方を勉強したり、手書きの練習をする場合もあるかと思います。
対策方法については、以下の記事を参照してください。
記述対策(春:3月~4月第1週 秋:9月~10月第1週)
記述試験対策では、参考書に収録されている問題を2周ほどしています。くまごろうの場合は参考書を2種類購入しているため、その時の習熟度に応じて2冊分をやっていることもあります。
特に記述系試験はその傾向が強いです。
不正解のものや引っ掛かりの覚えるものは、午後1のまとめを作成して、試験の前週に見直しをしています。
このほかにも人によっては記述の解き方を学習する必要があります。
対策方法については以下の記事を参照してください。
午前対策(春:3月第4週~4月第2週 秋:9月第4週~10月第2週)
午前対策は過去問暗記の要素が強いため、試験の直近に対策を行うことが多いです。
ただし記述試験に用語の穴埋めが多い区分(情報処理安全確保支援士など)については、単語自体を暗記する必要があるため、試験対策の初期に行うのが良いです。
対策としては過去問を5年分くらい行い、わからない問題をキャプチャしておきます。これを何回か繰り返して、過去問を暗記していきます。
対策方法については以下の記事を参照してください。
テスト前日
テスト前日は以下を行います。
- 記述試験のまとめを確認する
- 論文試験の骨子と演習論文を暗記する
- 論文で使用した漢字を暗記する
- 午前対策で取得したキャプチャを見直す
この辺は普通だと思います。
「論文で使用した漢字を暗記する」については、くまごろうは本当に漢字が苦手なため、書くのに不安を覚える漢字を一覧に書き出して(100個くらい)暗記をしています。
最近は効果が微妙だと感じるようになりました。もう受ける論文試験はないんですけどね。
テスト当日
基本的には午前1免除を得ているので、家を少し早く出て、会場近くのカフェで2時間くらい「テスト前日」で行ったことを再度確認しています。
また「テスト前日」に詰め込んでいることが多く、寝るのが遅いことが多いため、だいたいテスト当日は吐きそうになりながら試験を受けています。
テスト後はだいたい放心状態になるので、試験会場で休憩をしてから、5chの試験対策板を見ながら帰ることが多いですね。
試験対策の流れを理解いただけたでしょうか。
くまごろうは禿げそうになりながら(実際には白髪が増える)、吐きそうになりながら試験を受けています。
個別対策については順次作成していきますので、しばらくお待ちください。
今日の解説はここまでです。
また次回お会いしましょう。それでは!!
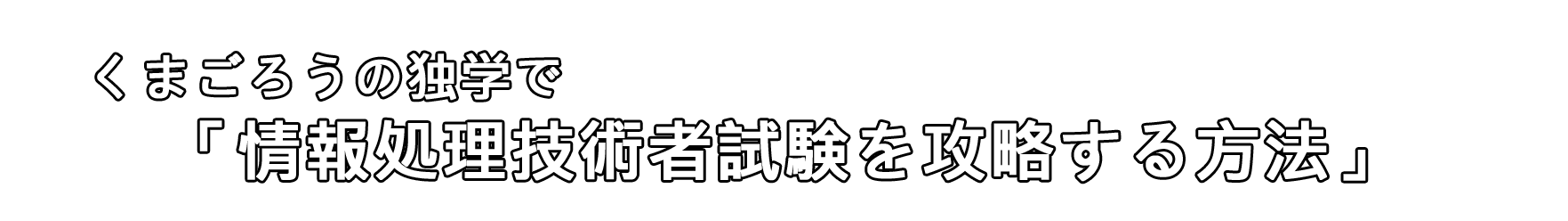












コメント